手術室看護師といわれると器械出し看護師のイメージが強いと思います。
この記事ではあまり知られていない外回り看護師の仕事を深掘りしていきます。
看護学生の実習や新人看護師の研修に役立つ情報も記しています。
情報収集

器械出し看護師を同じですが、手術を担当することになって最初に行うことは情報収集です。
同じ術式でも年齢や既往歴が変われば、手術を受けるリスクも変わります。
また腹腔鏡手術から開腹手術へ移行する可能性などもあるので、急変に対応できる準備をしていきます。
ココに注目!
- 何の情報が必要か
- 現疾患、既往歴、年齢、血液型、アレルギー、BMI、可動域制限、皮膚状態、検査データ(呼吸器系、心電図、血液など)
- 予定の術式
- 開腹や開胸への移行の可能性
- 前回のオペ記録、看護記録(2回目以降)
例えば、可動域制限がある場合は手術の体位がとれないかもしれません。
栄養状態が悪く高齢の患者であればスキンテアなどの皮膚トラブルや骨突出による術後の発赤なども想定できます。
考えられる可能性を吟味し外回り看護師としてできることを準備しておきます。
術前訪問

術前訪問では、手術前日などに病室を訪問し、手術に必要な情報を質問したり注意事項を確認したりしています。
手術を前にして不安を抱えている患者さんもいます。
業務的な質問ばかりをするのではなく、看護師として患者さんに寄り添った声掛けを行っていきましょう。
ココに注目!
- 何を質問しているか
- どのような流れで会話をしているか
- 会話中の姿勢、目線、声掛け
手術室看護師は患者さんと話せる機会が限られています。
その中でもしっかり話せるタイミングが術前訪問です。
”何を質問するか、どんな話をするか”を決めてから訪問しましょう。
カルテでは確認できなかった情報は忘れずに確認してください。
手術部屋の準備
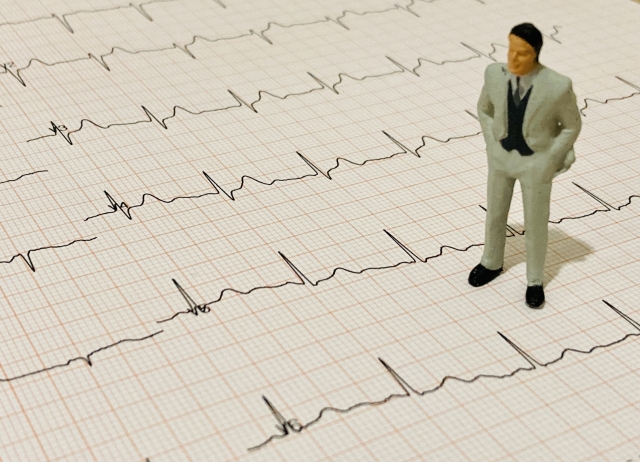
まずは心電図モニターや血圧計などの基本モニターがそろっているか確認します。
そして、手術によって使用する医療機器(電気メスなど)や手術台の種類が異なるので、手術に合わせたセッティングを行っていきます。
多量出血が予想される場合は輸血の解凍機なども準備しておかなくてはいけません。
ココに注目!
- モニター類などの基本準備
- 医療機器の種類やセッティング
- 手術台の種類、点検
- 輸液や生食の補充
- 空調の確認
慣れるまでは手術部屋の準備をするだけでも大変です。
ポイントは患者入室からの流れに合わせて準備をしていくことです。
”入室→モニター装着→ルート確保→麻酔導入→尿カテ挿入”の流れであれば、その順番に準備を進めていきます。
緊急手術の場合はゆっくり準備する余裕がありません。
患者入室の流れで準備する癖をつけておくと、急ぎの手術に対応する際もタイムロスを減らし質の高い医療の提供に繋がっていきます。
まとめ
外回り看護師の仕事は、手術前から盛りだくさんですね。
十分に経験を積むまでは、既往歴からリスクを予測するのは難しいことです。
まずは、基本の部屋準備からでよいので一歩ずつ進んでいきましょう。
頑張ったことは必ず自分の力になっていきます。
陰ながら皆さんを応援しています!



コメント